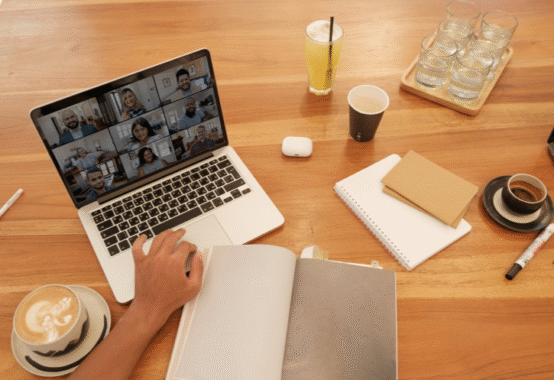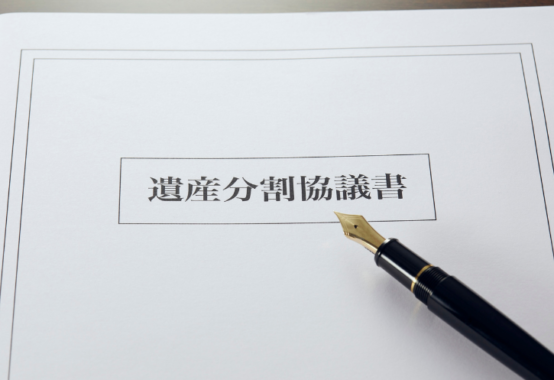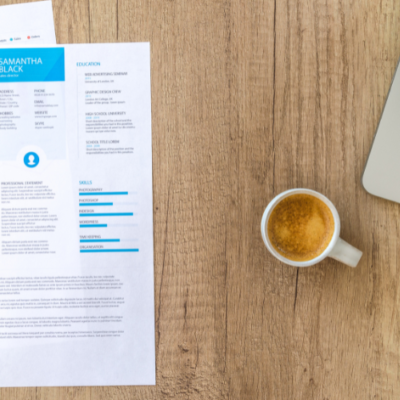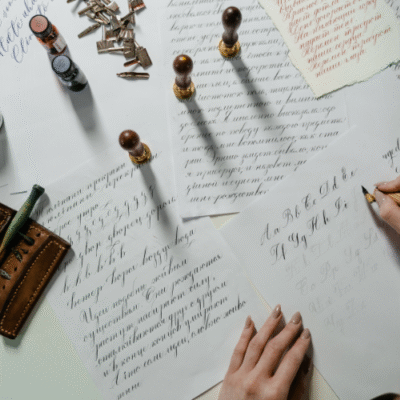相続手続きにおいて便利な制度のひとつが「法定相続情報証明制度」。
この制度を利用すれば、戸籍謄本などの束を何度も窓口へ提出する手間を省けます。
今回は、法定相続情報一覧図の作成に必要な書類と申請時の注意点についてわかりやすく解説します。
目次
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度は、比較的新しい制度で2017年5月29日から運用が開始しています。
被相続人(亡くなられた人)の法定相続人の範囲、相続人との関係等について、公的に証明してくれる制度です。
まず被相続人の戸籍謄本等の束を一度法務局に提出します。
その内容を登記官が確認し、「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を無料で作成してくれます。
この写しは、法定相続人が誰であるのかを証明することができます。
偽造防止措置を施した専用の用紙で交付してくれます。
そのため、この一覧図を使用すれば相続手続きの際に何度も戸籍謄本等の束を提出する必要がなくなります。
これにより、相続手続きを行う相続人はもちろん、手続きの担当部署双方の負担が軽減されます。
一覧図が無い場合、担当部署の方は戸籍謄本等の束から誰が法定相続人かを確認する作業が発生するためどうしても相応の時間がかかってしまいますが、一覧図があればすぐに誰が法定相続人かがわかるので作業もスムーズに進みます。
更に令和2年10月26日から相続手続きの他に、年金手続きにも使用可能となりました。
※ 相続手続で必要となる書類は各機関で異なりますので、かならず必要書類は提出先となる各機関にご照会ください。

申出は誰ができるの?
申出ができる人は以下の人です。
☑被相続人(亡くなられた人)の相続人
☑代理人
代理人となることができる人は以下の人です。
①法定代理人
②民法上の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
③資格者代理人(社会保険労務士、行政書士、司法書士,土地家屋調査士,弁護士,税理士、弁理士、海事代理士に限る。)
申出先はどこ?
申出ができる登記所は、以下の地を管轄する登記所の中から選ぶ事ができます。
①被相続人(亡くなられた方)の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出する方の住所地
④被相続人名義の不動産所在地
申出を登記所に行かずに郵送も可能です。
その場合、返信用封筒や切手等必要になりますので事前に登記所へご確認ください。

必要書類は?
☑申出書
(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書PDF)
(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書WORD)
(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書記入例PDF)
(出典:法務局HP)
☑法定相続情報一覧図
☑被相続人の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本又は全部事項証明書
☑被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票)
☑相続人の戸籍謄本又は全部事項証明書
☑申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは,これを証する書面
☑申出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書が必要となります)
代理人申請の場合には、委任状等も必要になります。
☑法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは,記載した住所を証する各相続人の住民票記載事項証明書(相続人の住所は任意の記載事項とされています。)
法定相続情報一覧図について
この写しは、相続手続きに必要な範囲で複数枚発行ができ、手数料は無料です。
この一覧図の保管期間は5年間となっており、その期間内であれば一覧図の写しを再交付することも可能です。
この再交付の申請ができるのは、始めに申出をした申出人に限定されていることに注意してください。
他の相続人の場合は、当初の申出人からの委任状が必要となります。
その他留意事項について
①被相続人(亡くなられた方)やその相続人が日本国籍を有していない等、戸除籍謄抄本を添付できない場合は、この制度はご利用できません。
②相続放棄した相続人がいる場合については、法定相続情報一覧図には氏名、生年月日及び続柄を記載します。
③法定相続情報一覧図の写しは、訂正印などで訂正はできません。
④法定相続情報一覧図の写しを手書きで作成する場合は楷書で記載します。
⑤遺産が預金のみの場合(不動産がない)でも、この制度を利用できます。
この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱になる場合がございますのでご注意ください。
当サイトに掲載する内容については細心の注意のもとに作成していますが、当サイトの情報を利用したことによる損害の賠償に対して一切の責任を負うものではありません。
ご自身で行ったものについては自己責任となりますのでご注意ください。
行政書士は戸籍収集や遺言書作成のサポートができます
戸籍の収集や遺言書の作成をご自身でされる場合、意外と手間が掛かり面倒です。
またせっかく作成しても法的に無効なものだと意味がありません。
①遺言書を作成されるお客様の手間を減らし、②遺言書を作成される方の意思が正確に反映される遺言書作成をサポートいたします。
法定相続情報一覧図や遺言書を作成しようかとご検討中の方は、遺言書作成サポート専門の新大阪サプール社労士・行政書士事務所をぜひご利用ください。
まずはお気軽にご連絡ください。
初回のご相談は無料です(30分)
お問い合せはこちらからどうぞ